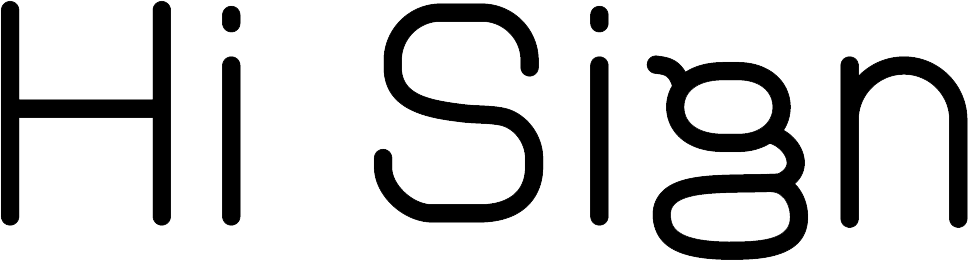エア看板 電源の疑問解消!屋外設置・電気代・安全対策ガイド
エア看板を導入しようとお考えの整骨院や飲食店、小規模店舗のオーナーさん、あるいはイベント主催者の方の中には、「エア看板って電源はどうすればいいの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。屋外で使うとなるとコンセントの確保が心配ですし、「常に電気が必要?」「雨の日でも大丈夫?」「電気代ってどれくらいかかる?」など、不安が尽きませんよね。
本記事では、そんな「エア看板 電源」にまつわるよくある疑問に寄り添い、わかりやすく解説していきます。エア看板の基本構造と電源の重要性から、屋外で安全に使うための方法、気になる電気代の目安、さらには雨天時の注意点やトラブル対策まで、順番にご紹介します。
この記事を読めば、エア看板の電源についてのモヤモヤがきっと解消されるはずです。それではまず、エア看板に本当に電気が必要なのかどうか、基本から見ていきましょう!
エア看板って電気が必要って聞いたけど、実際どうなの?
エア看板(エアー看板)は、その名の通り空気の力で立ち上がる大型のバルーン型看板です。土台部分に内蔵された送風機(ファン)が電源につながると自動的に空気を送り込み、写真のようにわずか数十秒で縦長のバルーンがパンと膨らんで自立します。この仕組み上、エア看板の使用には基本的に電気(電源)が必要です。送風を止めてしまうと空気が抜け、せっかく膨らんだ看板もしぼんでしまうため、利用中はコンセントにつないだ状態を保つ必要があります。
「電源が必要と聞くとちょっとハードルが高そう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。エア看板の電源は特別な工事や特殊な設備を要するものではなく、家庭用のAC100VコンセントでOKなんです。要するに、普段家電を使うのと同じ感覚で電源を取れば動きます。実際、多くの店舗やイベントでエア看板が活躍していますが、ほとんどはお店の屋内コンセントや屋外用の防水コンセント、延長コードなどを使って手軽に電源を確保しています。
次章では、そんなエア看板の基本構造と、「常時送風式」と呼ばれる特有の仕組みが電源にどう関わっているのかを、もう少し詳しく見てみましょう。
エア看板の基本構造と“常時送風式”ならではの電源の重要性
エア看板は大きく分けて「土台(台座)」「内部の送風機(ファン)」「内部のLED照明(ライト)」「バルーン(筒状の布地)」の4つのパートで構成されています。電源を入れると、土台の中にあるファンが回転して空気をバルーン内に送り込み、同時にライトを点灯させることができます。バルーン生地はファスナーやマジックテープで土台に固定されており、上部から常に空気が抜けていく“常時送風式”です。簡単に言えば、使用中はファンで常に空気を送り続けることでバルーンをピンと張った状態に保っているのです。
この常時送風式という仕組みにより、高さ3メートル級の大型看板でも安定して自立させることができます。一方で、先ほど述べたとおりファンを止めてしまうとバルーン内の空気が抜けてしぼんでしまうため、エア看板は電源を入れっぱなしで使う必要があります。そのため、電源ケーブルの取り回しや延長コードの使用方法、ブレーカーの容量など、電源まわりの取り扱いがとても重要になってきます。
ちなみに、最近のエア看板はLED照明を採用しているため、とても省エネです。昔の製品では水銀灯などを用いてトータルで300W以上消費するものもありましたが、LED化された現在の製品では送風機が約75W、LEDライトが15〜60W程度と合計100〜150W前後で動作するものが主流です。電力面でも無理なく扱えるよう進化しているんですね。
どんな電源が使える?屋外設置でも安心な方法とは
エア看板を使うにはコンセントが必要ですが、屋外で設置する場合、どのように電源を確保すればよいのでしょうか。ここでは、エア看板の電源を確保する主な方法について、それぞれのポイントを解説します。
家庭用コンセント(AC100V)でOK!
基本的にエア看板は家庭用のAC100Vコンセントでそのまま使えます。
店舗や会場の屋内コンセントに差し込めば、特別な工事なしですぐに膨らませることができますtrade-sign.com。多くのエア看板製品には約10メートル前後の電源コードが付属しており、屋外使用を想定してコンセントから遠く離れた場所にも届くよう配慮されています。
そのため、多少コンセントから離れた場所でも問題なく設置できます。
屋外用防水コンセントがあればベストですが、なくても延長コードで室内のコンセントから電源を取れます。ただし屋外使用時はいくつか注意点があります。
延長コードを使うときの注意点
屋内のコンセントから遠い場合は、延長コードで電源を延長しましょう。市販のもので構いませんが、屋外では防雨タイプのコードを選ぶと安心です。接続部分に水がかかってショートするリスクを減らせます。
延長コードを使用する際は以下のポイントにも注意しましょう:
- コードの配線は安全に: 人が歩く導線にコードを這わせる場合は、ガムテープなどで固定したり、ケーブルカバーを被せたりしてつまずき防止策を講じてください。また車が通る場所ではコードを保護チューブに入れるなど、踏まれて断線しない工夫が必要です。
- 差込口の防水: 延長コードとエア看板の電源プラグの接続部には、防水カバーを被せるか、ビニールテープでぐるぐる巻きにして水が入らないように保護します。市販の「延長コード用防雨コンセントカバー」を使えば簡単に防水できます。
- 過負荷に注意: エア看板自体の消費電力は小さいものの、延長コードに他の機器も多数繋いでいると合計で過負荷になる可能性があります。一緒に繋ぐ機器のワット数にも気を配り、可能ならエア看板専用に一本の延長コードを使うと安心です。
以上を守れば、延長コード経由でも安全にエア看板の電源を供給できます。
発電機を使う場合のポイント
近くにコンセントが無い場所では、発電機で電源を確保する方法もあります。エア看板の消費電力は最大約200Wなので小型インバーター発電機で十分です。ただし使用時は以下の点に注意してください:
- 燃料と連続稼働時間: ガソリン式発電機の場合、使用時間に見合った燃料を用意しておきましょう。エア看板を長時間使用するイベントでは、途中で燃料切れにならないよう注意が必要です。
- 騒音対策: 発電機は作動中それなりの音が出ます。静かなイベントや夜間では、なるべく低騒音型の発電機を選ぶか、人から離れた場所に設置するなどの配慮をしましょう。
- 発電機の容量: エア看板単体では200W以下ですが、他にも照明や音響機材などを同じ発電機で動かすなら、総電力に見合った容量の発電機を選ぶ必要があります。機器の合計ワット数の1.5倍程度の定格出力を持つ発電機だと安心です。
このように、現場の状況に応じて適切な電源確保方法を選べば、屋外であってもエア看板を問題なく使用できます。次に、皆さんが特に気にされる「電気代」について見てみましょう。
気になる電気代!1日使ったらいくらくらい?
エア看板を導入する際にもう一つ気になるのが電気代ですよね。「大きな看板だし電気を食いそう…」と心配になるかもしれません。しかしご安心ください。前述のとおりエア看板の消費電力はせいぜい100〜200W程度と小さく、電気代も比較的わずかです。
例えば消費電力150Wのエア看板を1日8時間運用した場合、消費電力量は1.2kWhになります。電気料金単価を仮に1kWhあたり27円とすると、1日あたり約32円の電気代という計算です。200Wで8時間でも1.6kWhで約43円程度にしかなりません。実際、エア看板を販売するメーカーの試算でも「1日8時間×30日で約1,000円」程度(=1日あたり約33円)と案内されています。
つまりエア看板の電気代は1日数十円程度と、とても経済的なんです。
長時間使っても1日あたりせいぜい数十円~百円未満程度です。月間で見ても1ヶ月毎日8時間使って1,000円前後、12時間点灯でも1,500〜2,000円程度でしょう。店舗の光熱費としてもごくわずかな負担で、電気代を理由にエア看板の導入を諦める必要はほぼないと言えますね。
屋外設置時の注意点とトラブル対策
最後に、屋外使用時の注意点や電源トラブル防止策を見ておきましょう。雨天時の扱い、ブレーカー対策、コード断線の予防策など順に解説します。
雨天時の防水対策
エア看板本体のバルーン生地は撥水加工が施されているものが多く、多少の小雨であれば弾いてくれるため問題なく使用できます。しかし、送風機や電源コードなど電気部分は水に弱いため、土砂降りなど悪天候時の使用は避けましょう
(多くのメーカーが「雨天時のご使用はお控えください」と注意喚起しています)。
どうしても雨の日に使用する必要がある場合は、次のような防水対策を講じましょう:
- 防水カバーの活用: エア看板の土台部分(送風機が収まっている部分)に被せる防水カバーやビニールシートを用意し、雨が直接かからないようにします。完全に密閉すると空気の吸入口を塞いでしまうので、適度に余裕を持ったカバーを被せると良いでしょう。
- 電源周りの防水: 電源プラグの接続部分には防水カバーを使って水の侵入を防ぎます。また、コンセントや接続部が直接水たまりに浸からないよう、高さを確保して設置してください。
- 異常時は電源オフ: 万が一、強風で倒れたり浸水したりして機器に異常が発生した場合は、ただちにコンセントからプラグを抜いて電源を切り、安全を確保しましょう。
雨の日でも適切に対策すればエア看板を使用できますが、安全第一で無理は禁物です。天候が悪化しそうなときは早めに撤去するなど、リスクを避ける判断も大切です。
ブレーカーが落ちないようにするには?
エア看板だけでブレーカーが落ちて電源が切れる心配はほとんどありません。なぜならエア看板の消費電力(約100〜200W)は標準的なブレーカー容量(15A=約1500W)に比べごく小さいからです。ただし、同じ回路に電子レンジや大型ヒーターなど電力の大きな機器を同時に繋いでいると、合計でブレーカー容量を超えてしまう可能性はあります。
ブレーカー落ちを防ぐためには、以下の点に注意しましょう
- 余裕のある回路を使う: エア看板を接続するコンセントの回路に余裕があるか確認します。他の機器で既に多くの電力を使っている回路ではなく、できればエア看板専用かそれに近い状態のコンセントを選びます。
- 分岐回路の活用: イベント会場などで複数のコンセントが用意されている場合、可能であればエア看板用に別系統(別のブレーカー)のコンセントを使わせてもらいましょう。分散して電力を取ることで一箇所に負荷が集中するのを避けられます。
- 定期的な確認: エア看板使用中に他の電気機器を追加で動かす場合、「バチッ」とブレーカーが落ちてしまう前に、一度どの程度電力を使っているか確認してみてください。会場の係員や電気担当の方がいれば相談するのも良いでしょう。
万一ブレーカーが落ちてしまった場合には、慌てずに不要な機器を減らす・回路を分けるなど対処した上でブレーカーを復旧させればOKです。エア看板自体は再び電源を入れればすぐ膨らみますので、トラブル後のリカバリーもしやすいですよ。
電源コードの断線・トラブル防止策
最後に、電源コードまわりのトラブル予防についてです。屋外でコードを引き回す以上、断線や傷には注意が必要です。以下のポイントを守って、安全に使用しましょう
- 過度な曲げ伸ばしをしない: コードを無理に曲げたり、折り曲げた状態で縛ったりしないでください。内部の銅線が断裂しやすくなります。収納時はゆったりと丸めて束ねましょう。
- 踏まれない工夫: 人通りが多い場所ではコードをマットの下に通す・テープで固定するなどして踏まれないようにします。車が通る箇所でコードを横切る場合は、コードプロテクターを使用して断線や感電を防止しましょう。
これらの対策を講じておけば、電源コードが原因でエア看板が使えない、なんてトラブルもぐっと減らせます。
以上、屋外でエア看板を運用する際の注意点を見てきました。それほど難しいことではありませんが、安全に長く使うためにぜひ覚えておいてくださいね。
まとめ:電源まわりで不安な方も、お気軽にご相談ください♪
エア看板の電源について、疑問や不安に感じやすいポイントを一通りご紹介してきました。おさらいすると、エア看板は常時送風のため電源が必要ですが、特別な工事は不要で家庭用コンセントで手軽に使えます。屋外でも延長コードや発電機を活用すれば設置場所を選びませんし、電気代も1日わずか数十円程度と経済的です。雨天時やコード取り扱いなど注意点はありますが、事前に対策しておけば安心してお使いいただけます。
「でもやっぱり自分で電源周りを準備するのは不安…」という方もご安心ください。当社ではエア看板の設置に関するご相談をいつでも歓迎しております!電源の確保方法や必要な設備について、専門スタッフが丁寧にアドバイスいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせ・ご相談くださいね♪
エア看板を上手に活用して、集客アップやイベント成功に役立てていきましょう!